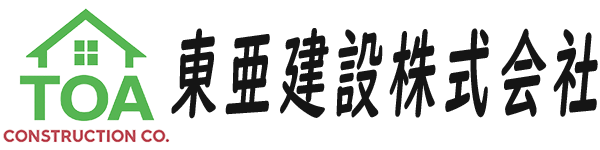建築基準法は1950年に制定され、耐震基準は1971年と1981年、2000年に大きな改正が行われました。
このうち1981年の建築基準法の改正によって、1981年5月31日までに確認申請を受けた 建物は「旧耐震」、1981年6月1日以降の確認申請を受けた建物は「新耐震」と呼ばれます。
旧耐震では「震度5程度の中規模の地震で大きな損傷を受けないこと」が基準となっていました。
これに対して新耐震では、「中地震では軽微なひび割れ程度の損傷にとどめ、震度6程度の大規模な 地震で建物の倒壊や損傷を受けないこと」という基準に変わっています。
1971年の建築基準法施行令の改正は、1968年に起きた十勝沖地震を踏まえたもので、鉄筋コンク リート造のせん断補強基準の強化が図られました。
柱に入る鉄筋のうち、主筋は縦に入り、帯筋は主筋のまわりに巻かれているものですが、 帯筋の間隔が30cm以内から10~15cm以内に改正されました。帯筋を増やすことで主筋を拘束し、 柱や梁のねばり強さを高め、コンクリートが破断し、建物が倒壊することを防ぐものです。
また、木造住宅では基礎を独立基礎から、連続したコンクリートの布基礎とするよう規定されて います。
現行の耐震基準は、主に1981年の建築基準法の改正によるもので、前述のように「新耐震」と いわれるものです。
1978年の宮城県沖地震を受けて改正が行われ、1995年の阪神・淡路大震災でも新耐震の基準を 満たした建物の損傷は少なかったとされています。
1981年の改正では、一次設計の「許容応力度計算」と二次設計の「保有水平耐力計算」の概念が 取り入れられました。
一次設計では、「中規模の地震に相当する、建物が支える20%以上の重さの水平力を受けても 損傷しないこと」を検証するもので、旧耐震と同様です。
二次設計は、大規模の地震に相当する建物が支える100%以上の重さの水平力を受けても倒壊 しないことを検証します。また、建物の高さや建物が建つ場所の地盤の性質などによる地震荷重の 違いを考慮して、実際の地震による力を反映したものとなりました。建物のねじれを防ぐため、 バランスに配慮した設計も求められるようになっています。
2000年の建築基準法の改正は木造住宅に関するもので、鉄筋コンクリート造のマンションの耐震基準は 1981年の改正以降大きく変わっていません。
基礎は地耐力に合ったものと規定され、木造住宅でも事実上地盤調査が義務づけられています。
また、柱や筋交いを固定する接合部の金物が指定されて耐力壁の配置のバランスも規定されました。